2023年01月09日
山梨ダルク、表彰された
「令和4年 安全安心な まちづくり関係功労者 表彰式」が2022年10月12日に開かれ 山梨ダルクが表彰された。同ダルクは 地域における社会貢献に取り組み、地域住民の理解と協力を得て、薬物等の依存からの回復を支援する取り組みを実施している。このような地域との共生を通じ、理解を得ながら依存からの回復を支援する取り組みは「山梨モデル」と呼ばれ、他の模範となっている。
以上、月刊「更生保護」2022年12月号 p.51から抜粋。

2019年12月13日
和歌山ダルク表彰された
和歌山弁護士会人権賞に 一般社団法人「和歌
山ダルク」(和歌山市)が選ばれた。和歌山弁
護士会から表彰状が贈られた。
和歌山ダルクは平成17年(2005年)に設立。
薬物やアルコールの依存に苦しむ人たちの回復
支援などに取り組んできた。
池谷太輔 代表が表彰式にでた。
以上 産経新聞2019年12月13日(金)和歌
山版の記事から抜粋。毎日新聞にも出ている
そうです。
和歌山ダルクは 14年の歴史のうちに 少な
くても三度, 大きいナンギを克服し、ここに弁
護士会から認められ、御同慶の至り。

この写真のサインボードの下の方に
since 2005 と薄く書かれてますが 写真では見えない。
2019年11月16日
近藤恒夫+岩井喜代仁・講演 お知らせ
2019年11月30日(土)開演10時~16:20
場所:大津市 明日都浜大津 4F.
ふれあいプラザホール
滋賀県大津市浜大津4丁目1-1
参加費 無料。
基調講演:
近藤恒夫さん:ダルク創設者。1985年 東京
日暮里にダルクを設立。
岩井喜代仁さん:茨城ダルク代表。13か所の
施設を設立。
参加申込・問合せ:びわこダルク
TEL 077-521-2944
主催:びわこダルク。共催:びわこ家族会、
全国薬物依存症者家族会連合会、東近江ダルク

2019年08月31日
京都ダルク 舞台作品になる
演出家・ダンサーの倉田翠が主宰する集団
akakilikeが 薬物依存症者回復支援施設「京
都ダルク」のメンバーとの舞台作品を8月17,
18日に京都芸術センターで上演した。メンバー
の日常をフィクションとして再構成した。
東京では 9月3日に荒川区のdー倉庫で上演さ
れる。
倉田はバレエを基礎に作品を制作している。
今作は倉田が1年半前にダルクのメンバーと出
会い、施設に通い生活を共にすることで生まれ
た。
「ダルク礼賛や更生のメロドラマといった単一
の物語に還元しない。彼らがこのように生きて
いる、その危うさも含めて直截に伝わる舞台」
と八角聡仁 教授(近大 文芸学部)は言う。
「これからもダルクに通い続ける」と倉田は言
う。
日本経済新聞 2019年8月23日(金)夕刊から
抜粋。

2019年06月21日
薬物依存めぐる現状と「刑の一部執行猶予」制度

月刊誌「創」から。
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190621-00010000-tsukuru-soci&p=1
上記URLを見てください。
薬物依存問題の専門家として知られる石塚伸一・
龍谷大学犯罪学研究センター長には、「創」は、
これまでも何度かインタビューを行い、いろいろな
事例について相談もしてきた。今回は、2016年
に再犯防止のために「刑の一部執行猶予」制度
が導入された後、実際にどう運用されているの
か、日本における薬物依存の実態はどうなって
いるのかなどを尋ねた。
2019年05月25日
薬物依存症者についての映画
「ベン イズ バック」という題。
Ben is back. であるらしい。
朝日新聞 夕刊 2019年5月24日(金)の記事
から抜粋:映画はクリスマスイブの朝、19歳の
ベンが治療施設を抜け出して実家に帰って来る
ところから始まる。町の住人は みなベンの
過去を知っていて、しだいに彼の罪の重さが
明らかになる。そして それでもなお息子を
愛し、信じ、守り、救いたいと願う母の心情も。
映画は薬物を巡る法律や環境の整備、金銭的な
問題を含めた施設の ありようにも 言及する。
東京・大阪などで5月24日から公開。順次各地
で。

2019年04月23日
「薬物依存症」本の紹介
表題は Dr.松本俊彦による ちくま新書。
筆者は依存症を「孤立の病」だという。安心
して人に依存できない病が 依存症なのだ。
自立とは 依存先を増やすこと。
医学的な治療の枠組みを超えて、社会設計レベ
ルの対処が必要なことが よく分かる。
以上、月刊 中央公論、2019年3月号、134p.
作家 川端裕人の記事から。

2019年04月13日
「生きのびるための犯罪」本の紹介
標記の本について 2019年4月12日金曜の朝
9時頃から NHKラジオ第一放送で紹介され
ました。7年前に出た本です。
版元に問い合わせたら 品切れでした。古本を
ネットで 探すしか ないです。
以下は 出版社のサイトから引用:
著 者: 上岡陽江+ダルク女性ハウス
定 価: 1404円(本体1300円+税8%)
出版社:イースト・プレス
ISBN: 9784781690537
発売日: 2012年10月4日
わたしたち、<暴力>がいちばんきらいです。
凄絶な当事者の語りは、人間を救う。
さまざまな暴力や虐待から、あらゆる手段を
もって生き延びてきた薬物依存症の女性たちの
おどろくべき子供時代と、回復への確かな道
のりを描いた本書は、人間の尊厳そのものを、
世代問わず、現代社会に生きるすべての人に、
深く深く問いかける。
さまざまなメディアから絶賛を浴びた処女作
『その後の不自由 「嵐」のあとを生きる人
たち』に次ぐ待望の1冊。マンガ、イラスト
多数収録。
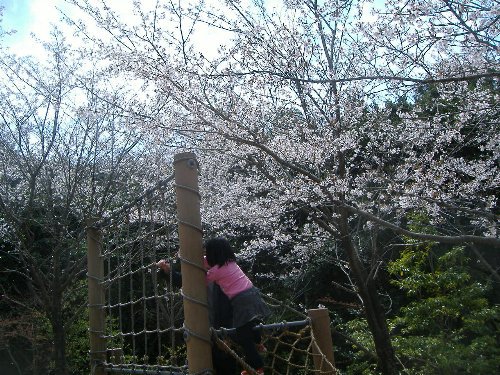
2019年03月27日
「中動態」とは
学校で習う英語で「能動態」と「受動態」が
でてくる。能動態では、人の意志が強調される。
意志に基づく行動の結果には、責任が伴う。
古代ギリシャ語に「中動態」があった。能動
とも、受動とも断定できない状態を表した。
現代社会で一例を挙げるなら、アルコール依存
などによる暴力だ。自己責任だとして非難され
るが、本人の意志だけでは克服が難しい。
哲学者、國分功一郎さんの著書「中動態の世
界」に教えられ、この記事になった。
以上 日本経済新聞 2019年3月16日”春秋”
から抜粋。

2019年02月23日
和歌山ダルク 普通に営業中
2月17日(日)に ある自助グループが和歌山
ダルクのスタッフ(男性)を講師に招いて 勉
強会を開きました。自助グループの世話人さん
が 電話で そのことを 当日 夜に知らせて
くれました:和歌山ダルクは 普通に操業して
いる とのことでした。
和歌山ダルクの AmebaowndのHPも アメ
ブロのブログも 一年以上 更新されていま
せん。
依存症者と その家族のために 和歌山ダルク
の現状を お伝えするために カキコミした
だけです。

2018年04月17日
りら創造芸術高校に感謝状
薬物防止を演劇を通じて啓発していることに
ついて りら創造芸術高校(紀美野町真国宮)
に厚労省から感謝状が贈られた。
女子高生が薬物使用に巻き込まれる「ドラッグ
ドロップ・フューチャー」を同校は2017年に
上演した。
下記サイトに ニュース和歌山の記事:
http://www.nwn.jp/news/180331_lira/
◎ dropには「麻薬取引の秘密中継場所」と
いう意味も ある そうですが、この芝居では
どういう意味か のし?

2017年12月05日
薬物依存症の専門外来/国立精神神経センター
薬物依存症の専門外来/国立精神神経センター
日本経済新聞2017年11月27日(月)から抜粋:
見出し-再犯防ぎ社会復帰促す。
国立精神・神経医療研究センターは薬物依存症
に特化した治療拠点の整備に乗り出した。東京
都小平市の病院内に9月、専門の外来を新設し
た。拠点は同センターの病院の外来に「薬物依
存症治療センター」の機能を持たせた。診療日
は週に一日で、専門の精神科医3人が診察する。
患者数は10月末時点で1日約40人前後。薬物
使用者が受診しても、ただちに警察に通報しな
い姿勢で対応する。
薬物の中でも覚醒剤は検挙された人に占める
再犯者の割合が6割を超え、年々上昇している。
一方で専門の医療機関は全国に約30ヶ所しかな
いとみられる。
★ブログ管理人の蛇足:和歌山県に薬物依存症
の専門外来はない。当分の間 開設される見込
みもない。

2017年09月28日
依存症は本人の意思ではどうにもならん
上村忠男、”中動態の世界”、月刊みすず、
2017年9月号 p.52~53.から抜粋。
インド・ヨーロッパ語族の動詞の態に、能動態
と受動態以外に「中動態」と呼ばれる態がある。
國分功一郎の新著「中動態の世界--意思と責任
の考古学』(医学書院、2017年)はエミール・
ぺバンヴェニストに依拠しながら、意志および
責任の倫理にまつわる問題との関連で「中動態」
の世界を論じる。
本書の冒頭には、薬物・アルコール依存症の
女性をサポートするダルク女性ハウスの代表
で、自身もアルコール依存の経験がある上岡
陽江とのやりとりをもとにしたという架空の対
話が「プロローグ」として置かれている。
そのなかで、上岡とおぼしき女性から依存症患
者の話しを聞いた國分とおぼしき男性が
<<そういう話しを聞くと、どうしても「しっ
かりとした自己を確立することが大切だ」と思
ってしまう自分がいるんですが・・・》と率直
な感想を述べる。すると、女性のほうでは
<<まあ私たちっていつも、「無責任だ」「甘
えるな」「アルコールもクスリも自分の意志で
やめられないのか」 って言われてるからね》
と応じたうえで、《アルコール依存症、薬物依
存症は本人の意志や、やる気ではどうにもでき
ない病気なんだってことが目本では理解されて
ないからね》とそうした言葉が投げかけられる
理由を説明する。そして男性が<<でも、やっ
ぱりまずは自分で「絶対にもうやらないぞ」と
思うことが出発点じやないのかって思ってしま
う》と述べたのにたいして、女性のほうでは
<<むしろそう思うとダメなのね》と答える。
《しっかりとした意志をもって、努力して、
「もう二度とクスリぱやらないようにする」
って思ってるとやめられない>>というのであ
る。
このプロローグからは、本書執筆の動機がどこ
にあったのかがわかる。「あとがき」には
<<「責任」や「意思」を持ち出しても、いや
それらを持ち出すからこそ どうにもできなく
なっている悩みや苦しさが そこにはあった>>
ともある。

2017年09月17日
ヘロイン依存・薬物使用室の運営@ドイツ(5
◎記者の問い:薬物使用室は役にたっている?
◎答え:はい。薬物使用室にかかわる人達は
薬物の扱いについて指導を受け、訓練されなけ
ればならない。あるいは使用者が この薬物を
お互いに注射できるように 取り計らわなけれ
ばならない。筋肉注射で入れるか 今は市場に
出回っているスプレーで鼻へ入れるかだ。
(つづく)
下記サイトから:
http://www.dw.com/de/tag-gegen-drogenmissbrauch-durch-prohibition-wird-das-geschaft-befeuert/a-39419899

2017年03月29日
断薬から始まる闘い
朝日新聞 2017年3月27日「患者を生きる」
物依存症・読者編(1)から抜粋:
下記サイトで有料で読むか、図書館で読んで
ください。読者編は5回 連載。
「患者を生きる」の連載は 有料の医療
サイトアピタルで読める:
http://www.asahi.com/apital/
「依存症」シリーズの届いた反響:
1.薬物依存症者から:
薬物を17年間つづけた人の通う病院の見解は
すべての依存症は完治しない、というものだ。
何十年と断薬していても、欲求が全くなく
なることはない。完治することはない。だから
「回復」を目指せ、と言う。
2. 薬物を使う男から離れた女性の話し:
依存症の人たちの話しをきくと、かつて
依存症だった人の手助けが効果的なようだ。
依存症から抜け出せた人なら、今苦しんで
いる人にどんな言葉をかけたらいいのか、
逆にそっとしておいてほしいのか、その人の
気持ちが よくわかるからだと思う。

写真提供:lovefreePhoto
2017年03月18日
薬物依存症・支援
朝日新聞 2017年2月10日「患者を生きる」
から抜粋。下記サイトで有料で読める。
あるいは図書館で読んでください:
覚醒剤で検挙されるのは毎年約1万1千人で
覚醒剤の再犯率は6割を超える。
治療は通院が一般的で、幻覚・妄想・興奮など
の急性症状があれば入院の対象となる。覚醒
剤急性症状は向精神病薬で比較的速く解消
できる。患者は栄養不良になっているので
体調の管理が必要だ。
薬物をやめられないことに対しては、ものの
考え方を修正して行動を変えることを目的と
した認知行動療法が基本になる。SMARPPプロ
グラムが2016年から公的医療保険の適用に
なった。16年末時点で全国29ヶ所の医療機関
と30ヶ所の精神保健福祉センターで実施され
ている。
回復するには 医療機関だけでなく、自助
グループや回復支援施設の役割も大きい。
薬物依存の自助グループはNAが代表的だ。
回復施設は日本では1985年に初めてダルクが
できた。今では ダルク以外の施設もある。
日本ダルクの近藤恒夫さんは「孤立こそ再
使用の原因。当事者が周りにいて、ひとり
ぽっちにさせないことが回復につながる」と
訴える。
「患者を生きる」の連載は 有料の医療サイト
アピタルで読める:
http://www.asahi.com/apital/

2017年03月17日
薬物依存症・入院から回復支援施設へ
朝日新聞 2017年2月8日「患者を生きる」
から抜粋。下記サイトで有料で読める。
あるいは図書館で読んでください:
覚せい剤で ついに底をついたマキさんは
2012年 奈良の薬物依存症者回復支援組織を
訪ねた。そこでの提案により大阪府富田林の
汐ノ宮温泉病院に三ヶ月入院した。幻覚や
妄想はなくなり、生活リズムを取り戻した。
退院の日に回復支援組織のスタッフが病院
まで迎えに来た。
「患者を生きる」の連載は 有料の医療サイト
アピタルで読める:
http://www.asahi.com/apital/

2017年03月08日
映画「トークバック 女たちのシアター」
ドキュメンタリー映画「Lifers ライファーズ
終身刑を超えて」の監督である坂上香の作品。
テーマは「表現」と「人の変容」です。サン
フランシスコを舞台に、HIV陽性者、元受刑者、
薬物依存の女性たちが演劇を通して、自らの
人生を取り戻していくドキュメンタリーです。
坂上さんの作品には、刑務所や更生施設が
よく登場しますが、それは、罪を犯した人々の
大半が、変容や回復を必要としているから。
また、舞台が海外である場合が多いのですが、
それは日本では見られない先駆的な取組みが
あったり、国内では様々な制約から撮影でき
ないという理由からです。単に海外の成功例
を紹介したいというのではなく、常に日本に
暮らす私たちの課題を見据えながら取材して
います。
下記サイトから:
https://motion-gallery.net/projects/talkback2013
http://talkbackoutloud.com/index.html
★去年 泉南で上映会がありましたが
あとで知った。

このブログは 特定の組織の広報活動として 書いている
ので ないから アクセスを増やさなくても いいのですが
ブログの中には アクセスを増やすことが お金になる
ブログも あると聞きました。そういうブログも このブログを
クリックして くれている らしい。
2017年03月06日
依存症対策 強化・厚労省
日本経済新聞 2017年3月3日から抜粋:
見出し:ギャンブル アルコール 薬物
依存症、全国に治療拠点
全都道府県・政令市 助言は相談員配置
2017年度に全都道府県と政令市で依存症の
専門医療機関を指定する。
来年度から「依存症相談員」をすべての都道
府県と政令市に一人ずつ配置する。相談員は
患者支援の経験者や精神保健福祉士などの
中から選ぶことを想定している。
★ブログ管理人の蛇足:
和歌山県で依存症の専門医療機関を指定さ
れても 薬物依存については 県内に専門
外来はないので 指定は 患者にとって
あまり意味は ない。和歌山の依存症者は
大阪の病院へ行けば いいと言うことだと
思う。 「依存症相談員」は今 県精神保健
福祉センタに おられまして 熱心にして
くれています。しかし 県内に専門医がない
というのは 辛い。

2017年03月05日
「刑の一部執行猶予制度時代の...
「刑の一部執行猶予制度時代のダルクと
その近未来」Freedomセミナー
2016年6月公布、施行された刑の一部執行
猶予制度は、一定期間の刑事施設内処遇の
後、残りの刑期に1年~5年の執行猶予を設け、
従来に比べて長い保護観察期間内に、再犯率
の高い薬物使用者の社会内処遇を実施し
ようとするものである。その運用にあたり
、医療機関のほか、連携団体として薬物依存
回復施設であるダルクもこの制度の一翼を
担おうとしている。このような統治機構との
協働における現状とその近未来について、
この分野に詳しい気鋭の二人の学者を迎え、
その方向性を占う。
講演1 清く正しく生きることが押し付け
られる時代の矯正処遇と社会内処遇
丸山泰弘 (立正大学法学部准教授)
講演2 参加か動員か――刑の一部執行
猶予制度をダルクはどう受け止めるのか
平井秀幸 (四天王寺大学人文
社会学部准教授)
パネルディスカッション 司会 倉田めば
(大阪ダルクディレクター)
とき:2017年3月26日(日曜日)13:15~
16:30(13:00開場)
ところ:新大阪丸ビル新館602号室(大阪市
東淀川区東中島1丁目18番27号)
参加費:事前申し込み¥1000 当日¥1300
事前申し込み:TEL・FAX:06‐6320‐1463
(Freedom) Mail:freedom7@a1.rimnet.ne.jp
この催しは平成27年に実施された共同募金配分
金を受けて実施されます。住民、寄付者の皆様
に感謝いたします。
講演1 清く正しく生きることが押し付けられる
時代の矯正処遇と社会内処遇
丸山泰弘 (立正大学法学部准教授)
【プロフィール】龍谷大学大学院博士後期課程
修了(博士〔法学〕)。龍谷大学法学部非常勤講師、
愛知大学法学部非常勤講師、龍谷大学矯正・
保護総合センター博士研究員などを経て、
2011年に立正大学法学部に着任。主な業績
として『刑事司法における薬物依存回復プロ
グラムの意義:「回復」をめぐる権利と義務』
(日本評論社、2015年)、編著として丸山
泰弘編『刑事司法と福祉をつなぐ』(成文堂、
2015年)など。
【報告要旨】 「刑事施設被収容者処遇法」
では薬物依存離脱指導が義務付けされた
と言われる。
また、刑の一部執行猶予制度においても、
薬物使用等の罪を犯した者に対する「再犯
防止のため」の処遇を行えるようになった。
従来の反省を促す刑罰一辺倒の制度
から見れば、より治療的で福祉的であると
見る研究者や実務家も多い。一部猶予に
ついては施行から1ヶ月間だけで134件
(内95%は薬物事犯)が言い渡され、裁判
官の期待も寄せられているように見える。
しかし、その実質的なサポートの部分は
DARCなどの民間施設に委託するにも
かかわらず、刑事司法による監視期間を
引き伸ばしただけのようにも思える。こ
ういった問題点を踏まえ、施設内処遇およ
び社会内処遇の功罪について話題を
提供したい。
講演2 参加か動員か――刑の一部執行猶予
制度をダルクはどう受け止めるのか
平井秀幸 (四天王寺大学人文社会学部
准教授)
【プロフィール】 東京大学大学院博士後期課程
修了(博士〔教育学〕)。横浜市立大学・昭和女子
大学・淑徳大学非常勤講師、カールトン大学博士
研究員などを経て、2011年に四天王寺大学
人文社会学部に着任。主な業績として『刑務所
処遇の社会学:認知行動療法・新自由主義的
規律・統治性』(世織書房、2015年)、編著とし
てダルク研究会編(南保輔・平井秀幸責任編集)
『ダルクの日々:薬物依存者の生活と人生』
(知玄舎、2013年)など。
【報告要旨】昨年(2016年)6月1日、「刑法等の
一部を改正する法律」及び「薬物使用等の罪を
犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関
する法律」により導入された刑の一部執行猶
予制度が施行された。同制度が主たる対象と
して念頭に置いているのが薬物使用等の罪を
犯した者であることもあり、今後は徐々に
“刑事施設出所者の保護観察処遇(薬物再乱
用防止プログラム)や帰住先のない一部執行
猶予者の受け入れ等の局面においてダルクが
どのような役割を果たすのか”という論点が
現実味を帯びてくると考えられる。 ところが、
(刑の一部執行猶予制度やそこでのダルクの
役割については、各方面から懸念が表明され
ている一方で)
実際に当事者となるダルクの側が同制度を
どのように意味づけ、それとの関係をどの
ように構築していこうとしているのかについて
の分析はほぼなされていない。当日は、現在
実施中の調査データの一部を紹介しながら、
上記論点に対する中間考察的な報告を
行いたい。








